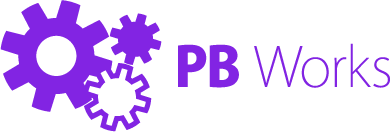紙袋の材質を徹底解説!本体・持ち手の種類と選び方

紙袋本体の材質について
紙袋をオリジナルで製作する場合、材質や印刷、サイズや加工等、様々な要素を組み合わせるオリジナル性は重要なポイントのうちの一つです。このオリジナル要素のうちの一つ「材質」には紙袋の持ち手の材質、本体の紙の材質、その他表面加工の材質等を指す場合もありますが、ここではまず紙袋本体の材質に注目。紙袋本体に使われている紙には大別して以下の種類があります。
それぞれを解説していきます。
クラフト紙
世に流通している紙袋の材質のうち、ほとんどは恐らく「クラフト紙」が占めていると思われます。というのも、大量生産向きの紙袋製作方法である、通称「フレキソ紙袋」(フレキソ印刷方式と輪転機を使って紙袋をほぼ自動で製作する方法)において、用紙にクラフト紙が採用されているために必然、紙袋全体に占める割合が多くなっているということだと思われます。基本的にフレキソ紙袋ではクラフト紙以外は使われません。なぜならクラフト紙の特性が、紙袋に求められる丈夫さと、製袋の際に施される「折り加工」に対する適正、この二つを満たしているからでしょう。クラフト紙の丈夫さは、例えば重たいものを入れる袋(お米用の袋、セメントを入れる袋等)に使われていることからも明らかです。折り加工に対する耐性もそれに由来するもので、折り曲げた時に紙割れが発生せず、強度も損なわれません。これがコート紙となると、折り加工の際に紙割れが生じてしまい、紙袋という製品としてはやや問題のある仕上がりとなってしまいます。このコート紙については別で書いてみたいと思います。
クラフト紙は更にいくつかの種類に分けられます。
の主に3つです。この3つの違いは、まず漂白をしているかどうか、という点と、表面を平滑に加工しているかどうか、という点です。この3つのうち、未晒クラフト紙は文字通り「晒していない」という意味で、具体的には漂白をしていないクラフト紙ということになります。漂白をすると紙は白くなり、晒クラフト紙になります。また、漂白することで少しばかり強度が落ちます。これは漂白が紙の繊維の強度に少なからず影響を及ぼすからです。強度を最も重要視するような紙袋では漂白は行わない方が良いでしょう。先ほど述べたお米やセメント袋が茶色いのは、この強度を重視した結果です。といっても一般的なショッピングバッグやイベント用の袋、持ち帰り用の紙袋では10kgを超えるような物を入れるというような状況はほぼないので、強度に関してはここではあまり問題にならないでしょう。どちらかというと、この漂白の工程はコストがかかるので、未晒クラフト紙が一番安価な紙だから、ということかもしれません。また、オーガニックっぽいルックスを優先した結果の場合も。
未晒クラフト紙

紙の厚みについて
紙には幾つかの種類の紙の厚みがあります。単位は「g/㎡」や「kg」が良く使われます。このうち「g/㎡」は1㎡の面積の紙の重さを表す単位なので、正確には厚みではなく重さなのですが、紙袋を作る際にはよく使われる単位です。一方で「kg」も重量で、その紙の1,000枚の重さです。例えば未晒クラフト紙でいうと、いくつかのサイズがあるのですが…… というように単位の話をはじめると少し長くなってしまうので、とりあえずここではいったん「g/㎡」を「g」(グラム)と呼ぶ事として厚みを表してみます。種類としては大体10g単位で50g、60g、70g、80g、100g、120g、といったラインナップがあります。もちろん数字が大きくなると厚みは増します。作る紙袋にもよりますが、50g〜80gぐらいまでは持ち手のない、「角底袋」と呼ばれる紙袋に比較的向いていて、それ以上の100g〜120gぐらいの厚みになると持ち手がついた、「手提げ紙袋」に向いています。紙袋の製法には色々な種類があるのですが、前述の大量生産に向いた紙袋で、比較的コストを重視した作り方である「フレキソ紙袋」と一般に呼ばれる紙袋には、この未晒クラフト紙が一番多く使われていると思われます。なんといっても一番安く、強度が高い紙となるとこの紙一択となるからです。ただ、コストに関しては様々な条件・状況もあると思いますが、例えば先ほどの大量生産向けのフレキソ紙袋の場合で考えてみます。大量に作るので未晒クラフト紙の場合と晒クラフト紙の場合で紙袋一枚の単価に仮に1円の差があったとした場合、極端な話10万枚作る場合はトータルコストで10万円のコストの差が出ることになります。一方で、小ロット製作で紙袋の500枚作る場合はトータルでは500円しか変わらないので、この差を担当者がどう考えるかで選択方法も変わってくるでしょう。アパレル店が小ロットでまずは500枚で考える場合、重いものも入ることはなく、コストで上記のような差しかないようであれば紙袋の材質はデザインの方が重視されることが多くなるでしょう。
クラフト紙への印刷

未晒クラフト紙はフレキソ印刷も可能ですがオフセット印刷ももちろん可能ですし、場合によってはフルカラーオフセット印刷で写真やグラデーションのような表現も可能です。そのような場合、材質としては茶色い未晒クラフト紙と、漂白された晒クラフト紙、あるいはカラー表現に若干有利な片艶クラフト紙では仕上がりに差が出ます。茶色の材質を味として利用するか、下地を白にしてフルカラーの表現力を取るかがコストより重視されることもあります。一方で未晒クラフト紙の茶色い材質をベースに、白でロゴ印刷したり、といったパターンも結構多く、なかなかカッコいい仕上がりになりますので人気の組み合わせです。
クラフト紙の印刷との相性
印刷との相性ですが、未晒クラフト紙はその表面の特徴として、コート紙等のように平滑ではなく、デコボコしているためにインキが沈みやすく、やや暗めの印刷の仕上がりになることが多いです。その為、あらかじめ印刷データを明るめの設定に修正しておいたり、または特色印刷などでも想定より明るめのインキを選択したり等の調整をすることがあります。仕上がりの感じを予めテストするケースもあり、実際にオフセット印刷機を使い、実際のクラフト紙に印刷することで「本機校正」を行うこともあります。校正をもとに再度データを修正したりインクの選定を変更したりとクライアントの想像する仕上がりイメージに近づけていきます。ただ本機校正にはコストがかかり、色数等の条件でも変わりますが数万円の校正費用を見込む必要があります。
晒クラフト紙

次に晒クラフト紙ですが、こちらも同様に文字通りクラフト紙を晒した(漂白した)もので、未晒クラフト紙からさらに漂白工程が増えるので、若干コストにも影響があります。といっても未晒クラフト紙のところでも書いたように、そのコストの違いをどのように捉えるかがポイントでしょう。漂白工程により、強度は若干落ちてしまいますが、こちらも内容物との兼ね合いのうえで、問題となるケースはあまり多くはないでしょう。未晒クラフト紙との違いは上記2つのポイントぐらいで、言ってしまえばほぼ茶色か白か、の違いです。印刷適性に関しても同様で、やはり表面がデコボコしているために仕上がりが沈んだ感じに仕上がりやすくなります。
片艶クラフト紙
上記の未晒クラフト紙、晒クラフト紙の二つは違いがほぼ色のみと言ってしまってもいいものだったのに対し、片艶クラフト紙はその表面の片面にさらに平滑加工を加えたもので、クラフト紙特有の印刷の沈み具合をある程度軽減したものです。といってもコート紙等と比較するとまだまだ印刷適性は及ばないのですが、これは加工方法がコート紙では塗工による加工であるのに対し、片艶クラフト紙では塗工ではなくあくまで紙の表面を平らにする加工にとどまることに起因します。ただやはり加工をしない未晒クラフト紙、晒クラフト紙紙と比較すると、まず紙自体にほんのり光沢があるのが特徴です。印刷の表現も、表面が平滑であることでインキの沈みが軽減され、写真等の明度は艶なしのクラフト紙と比較すると改善されています。

ただ平滑であることによる弊害もあり、まずインクの沈みが軽減されることで、インクの紙への定着力は通常のクラフト紙と比較して下がります。インクが定着しにくくなる事により、印刷してから乾きにくくなったり、こするとインクが取れやすくなったり、といった問題が出てきます。仕上がった紙袋同士が接触し、隣接した紙袋にインクが色移りしたり、紙袋を実際に使っている時に皮膚や衣服についたりと、少し厄介な問題が出てくることもあります。もちろんこれらの色移りの問題は、片艶クラフト紙に限った問題ではなく、表面が平滑だと起こりやすくなるというだけで、未晒クラフト紙、晒クラフト紙、延いてはどのような紙に印刷しても起こりうる問題ですので、それがより起こりやすくなる、というだけの話です。可能性の話になると、やはり印刷面積が大きければ大きいほど問題が起こる可能性も増すと言えます。紙袋の印刷では全面にベタの印刷を行うケースは比較的多く、事前に危険性は把握しておく必要はあるでしょう。
印刷インキの色移り対策
PPフィルムを貼る
クラフト紙への印刷に関する問題を解決するにはいくつか方法があり、一つは色移りを完全に防ぐために上からフィルムを貼る方法です。透明のPP(ポリプロピレン )加工を紙の上から施せば色移りの問題は完全に解決します。また、PPを貼ることにより紙袋自体の強度も上がりますし、耐水性も付与されます。いい事づくめですが、それに伴いコストがそこそこ上がってしまうのが問題と言えば問題かもしれません。
PPフィルムの種類
PPフィルムは主に2種類あり、光沢のあるグロスPP、光沢のないマットPPから選択できます。マットPPは光沢のあるグロスPPからさらにマット加工を行うのでその分若干コストが上がります。このPPフィルム加工ですが、そもそも色移り対策に行う加工というよりは、製品としての性質・特徴・魅力を付与するために行うことの方が実は多いです。また、印刷の発色・再現性という点においてはクラフト紙よりコート紙の方が優れており、その印刷をより魅力的に見せたい場合や、コート紙においてはPPフィルムを貼る加工は必須とされているので(この理由はまた別の項目で書こうと思います)、紙袋という製品においては、PP加工を行うケースの多くはコート紙の紙袋が対象になっています。
ニスを印刷する
クラフト紙の色移り対策の話に戻すと、フィルムを貼る方法以外ではいくつかあるのですが、ニスを印刷する方法も有効です。印刷系の方法では他にもプレスコート、ビニール引きといったものもあるのですが、コストと実用性の点からここではニスを詳しく説明しようと思います。と言ってもニス印刷は、オフセット印刷のインキを透明ニスにするという、至極シンプルな方法です。色移りのしそうなデザインの上から印刷し、透明の層を加えることで、色移りを起こりにくくしようということです。これは紙袋全体・全面の場合もあれば、部分的になケースもあり、例えば紙袋全体にベタ印刷がされていれば、同様に全体にベタ印刷しなければあまり意味がありません。反対に、部分的にロゴ部分だけの色移りを防ぐのであればそのロゴ部分だけの印刷で十分ではあります。ただ、印刷面積があまり広くなければ色移りの可能性も少なくなるので、そもそもロゴ部分だけの色移りに対策が必要かどうか、という別の話が持ち上がってきます。ここは印刷面積と色移りの危険性、コストや使い方等との相談が必要となるでしょう。また、その色移り対策そのものの効果ですが、ニスの場合はフィルムと違って透明インキの層が紙の最上面に形成されるだけなので、例えば使っているうちに紙袋が何かに擦れたりするとニス層が削れて印刷面が露出します。そうなると次に何かに触れた時には色移りしてしまいますし、また雨天等で紙袋が濡れてしまうと同様にニス層が剥がれやすくなってしまうこともあります。ですのでフィルムを貼るのと比較して、どちらかというと気休め的な意味合いが強い加工と言えるでしょう。紙袋を持ち帰る人が、店から家まで持ち帰るときだけ色移りを防いでくれれば良い、ということなら十分効果的でしょう。
コート紙
コート紙はクラフト紙と違い、表面にコート剤を塗布して表面を平滑かつ光沢のある(またはマット調に)仕上げにした紙です。表面が平滑なので、オフセット印刷等のインクが均一に乗り、印刷の再現性、発色が良好です。鮮やかなフルカラー写真やグラデーションの表現が得意で、カラフルな色調で目を引く紙袋の作成に向きます。コート紙は折り加工を施すと紙割れが起こりやすく、それを防ぐために表面にPPフィルム加工を施すケースがほとんどですが、このフィルムにより光沢感による鮮やかさが一層増したり、落ち着いたマットな高級感が付加されたりします。

コート紙の種類
紙袋製作に使うことのできるコート紙は主に2種あり、一般的な「A2コート紙」と呼ばれるものと、発色・光沢度・再現性・紙自体の白度がより優れた「キャストコート紙」がそれです。多くはA2コート紙が使われますが、印刷する内容、例えば商材や製品等のフルカラー写真をオフセット印刷にてより正確に表現したい場合、より鮮やかに、魅力的に見せたい場合など、印刷内容により重点をおいた場合に用いられます。オフセット印刷は基本的に色の構成要素をCMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の4つに分解し、それを4つの版で印刷し、重ね合わせて表現しますが、実際にオフセット印刷機を用いてフルカラー印刷を行う際、インクの盛り量を調整することである程度の色調調整をすることができます。例えば印刷内容のうち、この部分の写真をもう少し明るく、暗く、少し青っぽく、赤っぽく、といったことが印刷中にコントロールできます。もちろんコントロール幅には限界がありますが、コート紙、中でもキャストコート紙は色調のコントロールを用いてクライアントのイメージに近づけやすい紙だと言えます。
コート紙への加工
紙袋の材質にコート紙を採用する場合は、印刷の後PPフィルムを貼るケースがほとんどなのですが、PPフィルムを貼る際はフィルムを貼る事による色調の変化に気をつける必要があります。写真等のオフセット印刷(網点による印刷表現)の色調はグロス(光沢)PP加工を施すことでやや濃く、特に赤みを増す傾向があります。対してマットPP加工の場合は、若干彩度が抑えられ、落ち着く(沈む)傾向があります。これはフィルムの光の反射の仕方の変化、またはインクの網点が加工により若干潰れ、広がる事や、マット加工による表面の平滑度の変化などが原因です。それにより、PPフィルム加工を行う場合はある程度印刷の際に事前に濃さ(赤み)を押さえたり、若干狙った彩度より明るめに仕上げる、等の予想が必要になります。また一方でPP加工の際に必要となる圧着熱が原因でインクが変質し、色にも変化が生じてしまうというような場合には、ある程度低い温度で加工を行うことができるフィルムを使う、といったケースもあります。材質の話からは少し逸れますが、オフセット印刷を行った直後ではイメージぴったりの仕上がりだったものが、数十分後、または翌日になりインクが乾燥したのちに再度確認すると、例えば赤かったものが乾燥で青くなってしまったり、鮮明に濃く印刷されていたものが淡く、薄く変化してしまった、というようなケースも少なくありません。オフセット印刷は気温や湿度等の条件に非常に左右されやすい印刷方法なので、色調が非常に重要な部分を占めるような製品の場合は慎重に進める必要があります。
コート紙の厚み
一般に紙袋に使われるコート紙は基本は157g/㎡が多いです。通常紙袋に求められる強度を満たしている厚みです。ただ、紙袋の強度よりは、質感、しっかりとした感じや高級感を増す目的で更に紙を厚くしたい、という要望も少なからずあり、その場合はもう1ランク、2ランク上の厚みの紙を用意することも可能です。これはコート紙だけでなく、クラフト紙でもラインアップがあります。ただやはり厚くなる分折り加工が難しくなり、通常の製袋機械を通すことが難しくなると、予めトムソン加工で折り筋加工を行い、折りやすくした上で内職さんの手による製袋、となるケースが多いです。そうなると、用紙代に加えてトムソンの木型代、内職代、等コストが結構嵩んでくるので、予算に合わなくなったりするケースが多いです。ただ、数量や仕様によって海外での製作も視野に入ってくると、コストの面ではある程度抑えることもできます。最近では国内で使う製袋機、印刷機等は中国で使われている最新型のそれらの機械と比較してかなり古くなっていたり、技術的にも中国がかなりクオリティが上がってきていることもあり、提案の一つとして十分お勧めできます。
コート紙のコスト
コート紙のコストは前述のクラフト紙と比較すると若干高くなります。また、紙袋を作る場合はコート紙にPPフィルムは必須加工となるので、それをコスト比較の材料として鑑みると、用紙にかかるコストのみを見るとクラフト紙の2倍ぐらいになるでしょう。対して、紙袋全体のコストからすると、用紙がコストに占める割合は半分〜3分の1程度。詳しくは紙袋の詳しい仕様や枚数にも左右されますが、紙袋一枚単価でいうと30〜40円程度の差が出てくると思われます。詳しい条件により正確な見積もり出すことも可能です。
特殊紙
紙袋の製作において、上記のクラフト紙、コート紙以外の紙となるとやや特殊なものになってきます。例えば、既に色がついた紙、コニーラップやタントのような色紙です。これらの紙は、その紙の色自体を数種〜数十種あるラインナップから選択できます。希望の色があれば良いのですが、選択肢としてはやや少なめかもしれません。通常、紙袋全体にベタ印刷をする場合は通常の印刷料金に加え、ベタ印刷の特別料金、またベタ印刷なので色ムラや色移り、乾燥の問題、等少なくない問題と直面します。色紙であれば、それらの問題はある程度スキップできます。すでに色がついているのでベタ印刷の特別料金は不要、色移りも起こりません。またPPフィルムは特に貼らなくても良いでしょう。逆にコニーラップ等の色紙特有の風合いが特徴になります。
特殊紙への加工
ただ、例えば改めてオフセット印刷でロゴマークや、それこそ写真などを印刷することには向いていません。前述の未晒クラフト紙への白印刷の様に、下地が濃い色の紙の場合は印刷の表現が難しくなります。色紙へロゴを配置したいとなった場合にお勧めなのが、箔押しによるロゴ表現です。箔の色には意外と色々な色があり、特別金と銀のメタリックというわけではありません。赤や青、緑や紫等の通常色のラインナップも充実しています。もちろん白のご用意も。箔はインクと違って下地に対する隠蔽力が強く、下地が黒の紙の上に白の箔押しを行なってもそれほど下地の影響を受けず、しっかりと表現されます。色紙への加工でもう一つお勧めなのは、型押しによるロゴのエンボス加工です。金属の型を使い、ロゴマークを浮き出させたり凹ませたりすることで表現します。初回にはロゴの型を製作する版代が必要になりますが、1色のオフセット印刷をおこなうぐらいのコストでエンボス加工は行えます。前述の箔押しと組み合わせて箔のロゴを浮き出させたり、勿論オフセット印刷と組み合わせたり、そもそも白い紙、クラフト紙やコート紙にも施すことができる加工なので、意外と多くのバリエーションが考えられるでしょう。
カード紙

カード紙とは板紙とも呼ばれ、コート紙等と同様に印刷適性に優れた表面を持つことに加え、厚みを持たせたものです。紙袋の他にも、ある程度厚みや耐久性が必要な製品、例えば箱やハガキ、カード類や書物の表紙に使われます。通常のコート紙の紙袋にさらなる高級感を加えたいときや、紙袋では少ないですが単純に強度が求められる場合に選択肢に入ってきます。ただ紙袋の場合は前述のように紙が厚くなると折り加工の際に問題となる場合があり、予めトムソン加工による折り罫加工、内職作業によるコストの増加などが視野に入ってきます。少し細かい話になりますが、紙袋の側面マチの部分には折り加工の罫線が集中する箇所が左右それぞれ1カ所ずつ、計2カ所あります。コート紙の157g/㎡ぐらいの厚みではそれほど紙が硬くないので罫線集中箇所には折りの力は分散され、それほど無理な力が掛からず問題ないのですが、紙の厚みが増した場合、折り加工の際や実際に紙袋を使う際、無理な力がダイレクトに集中箇所にかかってしまうことになり、その箇所が磨耗等で破損しやすくなるという意外なデメリットもあります。具体的には、紙袋の実際の運用時、畳まれている紙袋を取り出して広げる際に集中箇所が破損する事が稀にあります。
カード紙のコスト
カード紙の紙袋は国内、国外で製作することができますが、国内では別途トムソン加工代や木型代など別途費用が発生する事に対して、海外で制作する際は基本的にどのような紙袋でもトムソン加工が前提となっており、別途費用の意味合いが薄いという意味ではコスト的に有利かもしれません。
環境に配慮した材質
昨今、地球環境に配慮する国連のSDGs提唱等、目にする事が増えました。環境に対する関心が急速に高まっている実感があります。普段お問い合わせを頂くなかにも、紙袋に限らず環境に配慮した素材・製品への切り替えや導入を実際に検討している企業が急増しています。弊社でも多数の環境配慮系製品の取り扱いがありますが、事紙袋に関する環境配慮材質となるとあまり選択肢がないのが現状です。元々紙という素材はパルプから作られていて、プラスチックとは違い環境に留まり生態系に影響を及ぼす材質ではありません。ただ、森林伐採等で植物が減り、二酸化炭素の排出量を増やしている、という意味では環境に与える影響は少なからずあると思います。この件に対応した素材としては、近年ドイツのFSCという森林認証組織が発行している、FSC認証製品というものが有名です。これは、適切に管理された森林から生産された木材を使い、適切に管理された労働環境を経て製造されたパルプ・紙を使っているという証明の認定を受けた製品です。国内でも最近はよく見かける製品で、認定マークが製品に印刷されていることもあり、周知が進んでいると思われます。ただこのFSCの認定には少し敷居の高い条件とコストが必要で、弊社での取り扱いは一部でしかまだ行えておりません。ただ今後主流になる認定マーク候補であるとは思われます。
その他、紙製品では「再生紙」はかなり以前から一般的に使われています。リサイクルされた紙が材質に含まれている場合、古紙パルプ配合率の表記をマークとして印刷する事ができます。R100、R80等のマークは普段一度は目にした事があると思いますが、この数値がリサイクル率を表すものです。古紙をリサイクルして再度紙にするのは一般的に少しコストのかかる話ですが、紙の価格としてはそれほど目立った価格の上昇はありません。ただ、リサイクル紙はその性質上、紙の品質(白さ等)に関しては若干不利ではあります。といっても白さが大きく損なわれるものではありません。飽くまでよく見てみると白度が落ちる、といったレベルです。
持ち手の種類・材質について
紙袋の持ち手は様々な種類があります。材質という区分においては、大きく3つに分かれます。
プラスチック系
ハッピータック、PP紐がこれにあたります。紙袋を再生用に廃棄する場合、紙とは分別する必要があります。
PP紐(PPロープ)

ポリプロピレンの材質で、持った感じは柔らかく、手にやさしい感触。数十色の色や、幾つかの太さを選択できます。持ち手の中では比較的低コストの部類になります。手軽に使える反面、高級感には欠けるので、用途によっては相性を考える必要があるでしょう。よく使われる用途には、寺社仏閣、和食懐石料理店、等の少し和風寄りのジャンルが目立ちます。
ポイント:低コスト・和風
ハッピータック

プラスチックの材質で、紙袋本体に穴を開け、その穴を挟む形で手作業で取り付けます。持った感じはカッチリとした丈夫な感触。数十色の色の中から選択が可能です。白と黒以外は少しですがコストが高くなります。持ち手の中では比較的標準コストの部類です。丈夫で固いイメージからか、学校や企業イベント、営業ツール等の真面目なシチュエーションでの活用が多いです。
ポイント:真面目なイメージ
紙系
紙三本、紙単紙、紙平紐がこれにあたります。紙袋の材質が全て紙製となるので、分別する際も紙ゴミとして扱えます。
紙三本

材質は紙。名の通り紙紐を三本撚ったもので、持った感じはややガサガサとした感触。数十色ある中から選択可能です。また、この三本の色をそれぞれ違う色にすることもできます。持ち手の中では比較的低コストの部類。小ロットでの製作の他、OFJタイプの中ロット、大量ロットでのフレキソ紙袋など製作方法の全てに対応した持ち手です。小ロット以外の取り付け方法では機械での自動取り付けとなり、コスト削減にも貢献。全体的に色々な用途に向きますが、若干高級感には欠けるところがあります。
ポイント:低コスト・紙袋製作方法の全種類で選択可能
紙単紙

紙を捻って一本の紐にしたものです。持った感じは紙三本と近く、ややガサガサとしています。数十色から選択できます。持ち手の中では標準的なコストの部類。小ロットでの製作の他、OFJタイプの中ロット、大量ロットでのフレキソ紙袋など製作方法の全てに対応した持ち手です。小ロット以外の取り付け方法では機械での自動取り付けとなり、コスト削減にも貢献。全体的に色々な用途に向きますが、若干高級感には欠けるところがあります。
ポイント:標準的なコスト・紙袋製作方法の全種類で選択可能
紙平紐

紙帯を折りたたんで一本の平紐にしたもの。四角形の形状が特徴で、持った感じは紙特有のガサガサとした感じです。いくつかの色の中から選択できますが、選択肢は他の持ち手と比較すると少し少なめ。最大の特徴は機械による自動取り付けで、最も安価な持ち手なことと、大量製作方法であるフレキソ紙袋での使用がほとんどであること。持ち手は紙袋内部に折り畳まれて仕上がり、持ち手を外に出してから使います。コンパクトなので保管スペース問題にも貢献できます。高級感には欠けるところがあり、どちらかというと低コスト大量生産を活かした用途に向きます。
ポイント:最も低コスト・省スペース
アクリル繊維系
アクリルスピンドル丸紐、平紐がこれに属します。アクリル繊維とは、セーター等の衣服などにも使われている合成繊維で、ウールのような柔らかさと風合いを持つ素材です。プラスチックと天然素材をミックスした材質で、廃棄の際には厳密には普通ゴミとなります。
アクリル丸紐

アクリル製の丸紐を紙袋の持ち手にしたもの。持った感じは柔らかく、標準的な紙袋の持ち手といえます。多数の色から選択でき、太さも数種類から選択可能。小ロット製作の場合は紙袋に穴を開け、結び目で取り付ける方法が一般的。またOFJタイプやフレキソタイプでも選択が可能で、こちらは機械による自動取り付けです。自動取り付けの場合は紙袋内側へ粘着テープでの取り付けとなり、結び目がない分省スペース管理が可能。安っぽい印象はなく、仕様の組み合わせによって高級感を出したり低コストで製作できたりと、作成可能な仕様を幅広くカバーします。
ポイント:標準的な持ち手・幅広い用途をカバー
アクリル平紐

上記のアクリル製の丸紐と同素材で、丸ではなくテープ状に平たくしたものです。持った感じも同様に柔らかく、標準的な紙袋の持ち手といえます。多数の色から選択でき、太さも数種類から選択可能。小ロット製作の場合は紙袋に穴を開け、結び目で取り付ける方法が一般的。またOFJタイプでも作成が可能。逆にフレキソタイプでは今のところ作成はできません。見た目の印象としては、丸紐よりは高級感が増し、それと共に持ち手の中でも最も高コストな部類となっています。アパレル用等、高級さやデザイン性を重視したものに向いています。
ポイント:高コスト系持ち手・どちらかというと高級感あり
その他の持ち手
パイレン紐

パイレン紐(パイレンロープ)はエクセルフィラメントとも呼ばれます。アクリル丸紐の素材に上質な光沢を持たせ、高級感を強調したものです。それと共にコストも高くなります。
ポイント:高コスト系持ち手・高級感あり
手抜き穴
これは持ち手を取り付けるというよりは、紙袋本体に楕円形の穴を開けてそこを持ち手とするものです。他に部材を必要としない分、低コストで製作が可能です。
ポイント:低コスト系持ち手・ある程度の最小ロット(2,000〜3,000)が必要
その他
ハトメ
紙袋本体に穴を開けて持ち手を取り付ける際、穴の強度を増すためにハトメを取り付け、そこに紐を通す加工です。追加でコストが必要ですが、単純に紙袋の強度がアップすることと、紙袋の見た目に高級感も付加されます。ハトメの色は数種類の中から選択が可能、また穴の大きさも調整できます。
ターントップ
紙袋への持ち手の取り付け方法を、穴をあけて紐を通すのではなく、紙袋口部分の折り返しの折り目あたりに切れ込みを入れ、そこから紐を露出させる方法です。穴がないので紙袋がすっきりシンプルに仕上がる事と、結び目を排除出来るので重ね合わせた時の容積が圧縮され、スペース問題にも貢献。
環境配慮に関して
持ち手全般に言える事ですが、現在では特に環境に配慮した材質が選べない状況です。といっても紙の持ち手であればリサイクルに回せますし、プラスチック製であればプラゴミとして分別できます。
その他の部分の材質
底ボール紙
紙袋の本体の材質に関しては、上記で大体紹介できたと思います。あとは紙袋の持ち手(ハンドル)や、底ボール紙を残すところでしょう。底ボール紙に関しては、ほぼ1種類で「コートボール」と呼ばれる厚紙が使われている事がほとんどです。片面が白、裏面が鼠色の紙で、紙袋の内側の底サイズに合わせてカットされ、紙袋の中に設置されているもので、特筆するところは特にないものです。ただ、完全オリジナル製作の紙袋において、稀に紙袋の内部の色もコントロールしたいという場合があります。例えば内部を全て真っ黒にしたいので、底ボール紙も黒で表現したい、等です。こういった場合、例えばカード紙を使った高級紙袋においては、カード紙に紙袋デザインを印刷する際に、紙の余白に底紙用のエリアを作り、一緒に印刷を行なってしまった上で紙袋本体と同様PPフィルム加工を行い、断裁で底紙にしてしまう、といったケースもあります。この方法だと用紙の不要なエリアを使って作るので、コストへの影響があまりなかったりします。同様のケースはボトル用紙袋等、紙袋の幅とマチが非常に近いサイズ(底が正方形に近い)の場合、底の強度を補強する底紙を作成する際にも用いられます。印刷を行えるので、補強用の紙と実際の紙袋の底部の色を合わせる必要がある場合には有効です。
分別ゴミに関して
紙袋の廃棄の件で補足しますと、例えばもしコート紙にPPフィルム等のプラスチックの加工を付加した場合は、厳密にいうと紙とプラスチックが混在する状態になりますが、家庭ゴミとして処分する場合は自治体によっては紙ゴミとして出す事が可能です。分別の際には比重の違いで材質を分別できる工程があるという事です。詳しくは自治体に確認が必要でしょう。